― クロノ&シロロが語る、古着のリアルな未来 ―
序章:おしゃれの裏側にある、知られざる現実。「闇REARITY」が古着業界の闇を解説
 シロロ
シロロ「ねぇクロノ、最近“古着女子”とか“古着男子”って多くなってない?」



「そうだね。でもね、古着ってトレンドの裏に“リアル”な一面もあるんだ。」
古着といえば「エコ」「個性」「かわいい」。
そんな明るいイメージが浸透していますが、その裏では仕入れ・在庫・環境・倫理など、さまざまな問題も潜んでいます。
今回は、知的で穏やかなクロノと、天然で明るいシロロが、
“古着業界の光と影”をやさしく、少しポップに語ります。
1章: 古着業界ってそもそもどういう世界?



「古着って“誰かの時間を引き継ぐ服”なんだ。でも最近は、その意味がちょっと薄れてきてる気もする。」



「え〜、私、“安くて可愛い”だけかと思ってた!」
古着業界とは、リユース(再使用)を軸にしたファッションビジネス。
Z世代を中心に「サステナブル」や「個性派ファッション」として人気が高まっています。
2023年には、日本のファッションリユース市場は1兆円を超える規模に成長しました。
フリマアプリやオンラインショップも活発で、「古着は特別なもの」から「身近な選択肢」へと変わりつつあります。
ただし、ブームの裏では“ビジネスとしての難しさ”も増しています。
2章: “闇”の構造:何が問題になっているのか



「クロノ、“闇”ってどんなこと?」



「大きく分けて、4つの課題があるんだ。」
2-1. 仕入れと在庫のリスク
古着屋が増えすぎて、仕入れ競争が激化。
人気ブランドやヴィンテージは取り合い状態で、価格がどんどん高騰しています。
特に都市部では家賃も上昇。
「ブームだから出店すれば儲かる」と思って参入したものの、
在庫が回転せず、数年で撤退するケースも珍しくありません。
2-2. 価値の伝え方が難しい
古着の魅力は、「一点物」や「時代のストーリー」。
でも、それを伝えきれないと、ただの“中古服”になってしまいます。



「服の価値って“物語”なんだ。誰が着て、どんな時代を生きてきたか。」



「なるほど〜!それを知ると、服がちょっと特別に見えるね。」
今は“服の良さ”だけでは売れず、“人の思い”を伝える力が問われています。
2-3. サステナブルの“矛盾”
古着は環境に優しいと言われますが、実はその構造には矛盾もあります。
大量生産された服が“余剰在庫”となり、
それを「リユース」という形で流通させているだけのケースも多いのです。
さらに、海外では安価な労働環境で仕分けやリメイクが行われることも。
「サステナブル=完全にクリーン」とは言い切れません。
2-4. ブームの終焉と淘汰
SNSを通じて広がった“古着ブーム”。
でも今、その波は少しずつ落ち着き、次の段階に入っています。
店舗が乱立し、似たようなラインナップばかりになり、
「どの店も同じに見える」という声も増加。
下北沢や高円寺などの人気エリアでも、
家賃上昇と客離れが進み、“淘汰”の時期に入っていると言われています。
3章: 希望の光:業界が進化する動き



「でも、希望もあるんだ。むしろ今が“本当の進化”のタイミングなんだよ。」



「へぇ〜、どんな進化?」
3-1. 市場の拡大と意識の変化
古着やリユース市場は、2030年には4兆円規模まで拡大すると予測されています。
背景には、「環境配慮」「個性重視」「一点物志向」といった価値観の変化があります。
「新品=正義」だった時代から、
「自分らしい=正義」へと価値観が移りつつあるのです。
3-2. ストーリーを売る時代
成功している古着屋は、服を“売る”のではなく“伝える”。
たとえば、「なぜこの服を選んだのか」「どこから来たのか」をSNSで発信。
バイヤー自身の哲学や審美眼が、お店のブランドそのものになっています。



「今は“誰が選んだか”がブランドになる時代なんだ。」



「服より、選ぶ人が注目されるってことだね!」
3-3. 街と文化の融合
下北沢、高円寺、中崎町…。
古着屋は今や“地域文化”の担い手でもあります。
ただ服を売るだけでなく、アート展示や音楽イベントを開くなど、
“街のカルチャー拠点”として再評価されているのです。
4章: これからの古着業界はどこへ向かう?



「これから大事なのは、“透明性”と“理念”だね。」



「服を売るだけじゃないんだね〜。」
4-1. “本物のサステナブル”へ
これからは、「どこで、誰が、どう作り、どう流通しているか」が明確なブランドが信頼を得ます。
消費者も“安さ”より“背景”を選ぶ時代に。
透明性を高め、誠実に発信することが、未来の古着屋に求められています。
4-2. キュレーター型古着屋の時代
ただ服を並べるのではなく、“価値観で選ぶ”。
そんな店が増えています。
オーナー自身が文化の発信者となり、
“この人が選んだ服なら間違いない”という信頼がファンを呼ぶのです。
4-3. デジタルとの融合
オンライン販売、ライブ配信、AR試着――。
古着業界にもテクノロジーが浸透しています。
「店に行かなくても、服のストーリーに出会える」。
そんな新しい買い物体験が広がりつつあります。
5章:古着を“知って選ぶ”時代へ
古着業界の“闇”を知ることは、
楽しみを奪うことではなく、楽しみを深めることです。
服を手に取るとき、少しだけ想像してみてください。
- この服は、どんな旅をしてきたのか?
- 誰の手を経て、いまここにあるのか?
- なぜ自分はそれを選ぶのか?
その想像の先に、“本当のファッションの豊かさ”があります。
終章:闇を超えて、文化へ
古着業界は今、ブームから文化へと進化する時代に入りました。
淘汰の波を超えて残るのは、
“本当に好きな人”と“本物の価値を見抜ける人”。



「光と影、両方を知ってこそファッションは深くなる。」



「うん。古着って、人と人、時代と時代をつなぐ服なんだね。」
服を“買う”のではなく、“迎える”。
その小さな選択の積み重ねが、
これからのファッションをつくっていくのです。
闇REARITYでは、これからも業界の闇をリアルにお伝えしていきます。
最新情報や体験談を通して、皆さんが業界の裏側を知る手助けになれば幸いです。
クロトとシロロの雑談「情報の闇」



「クロト〜、ネットってなんでも知れるね!」



「うん、でも本当のことが“全部”見えるわけじゃないんだ。」



「えっ、じゃあ私の検索も見られてるの!?」



「“おすすめ”って、君の心を映してる鏡みたいなものだよ。」



「うわ〜、昨日“ケーキ”検索したら広告だらけだった!」



「甘い情報ほど、心を引き寄せるんだ。」



「じゃあ今日は“自由”って検索してみよう!」



「ふふ、出てくるのは“働き方セミナー”かもしれないね。」
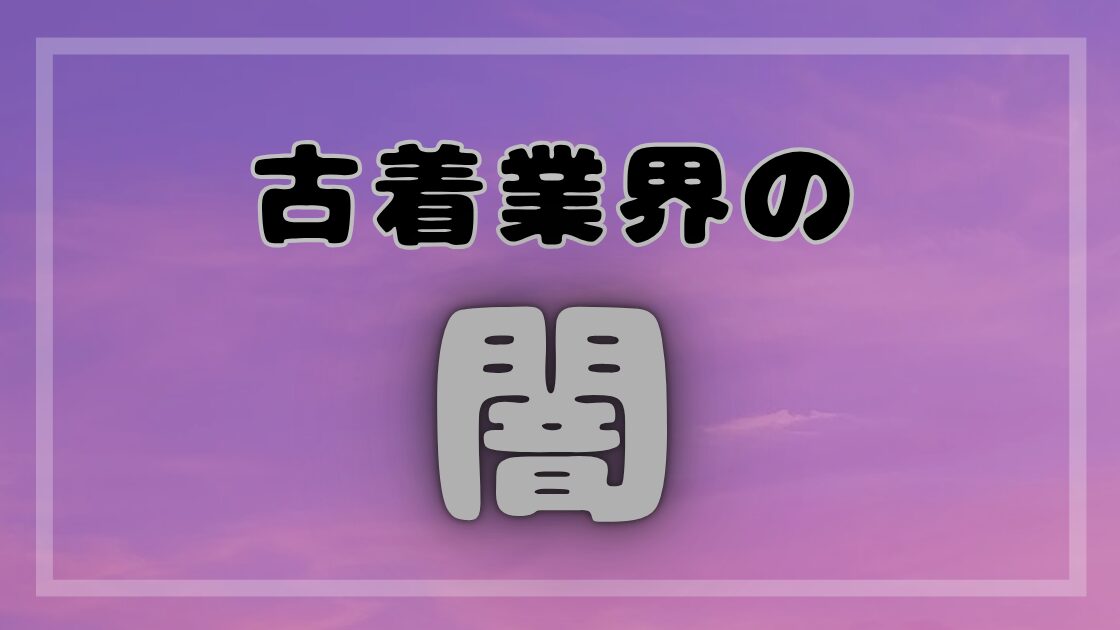
コメント